6月の梅雨明けという記録的猛暑の今年 (2025) 7月、典型的な熱中症になった患者さん (69歳・女性) がいた。予想される長い夏を前に、これを見過ごすわけにはいかない。かならず回避できる原因があるからである。

診察は2025年7月4日。
熱中症になったのは7月1日のことだったという。
症状は…
- 体に力が入らない
- 手が震える
- こむら返りを数回繰り返す
それまでの経過は…
- その日の朝6時〜7時45分まで日陰で草引きをした。
- 8時に朝食を摂る。熱い味噌汁を飲んだ。
- 引き続いて洗濯・掃除などの家事を行った。
そして午前10時、上記の症状が出る。たまたま午前診最後の患者さんだったので詳しく問診できた。
「まちがいなく熱中症ですね。なんで症状が出たと思いますか? 」
「草引きでしょうか…。熱中症にならないように気をつけて、涼しい間にしたんですが…。」
「草引きが直接の原因ではないです。草引きは8時には終わっているし、そのあと普通に朝食も摂っているし、熱中症になったのは10時ですからねえ。草引きが原因ならその最中か直後に起こすはずです。」
「朝食に熱い味噌汁を飲んだんです。もちろんそんなアツアツというわけではないんですが、それが原因でしょうか?」
「美味しくいただいたんでしょ? だったらありえないですね。それが原因なら、熱い飲み物が不快に感じるはずです。」
「疲れが溜まっていたんです。それまでの一週間ちょっと忙しくしていて、それが原因かなって。」
「疲れの蓄積は “火薬” の蓄積にはなります。しかし、熱中症にはそれなりの “引き金” があるはずです。それが分からないと、また起こす可能性があるんです。」
「他は特に思い当たることはないです。」
「さっき熱い味噌汁が原因かもとおっしゃいましたね。ここから想像できることなんですけど、ちょっと考え過ぎておられるかもしれません。熱い味噌汁は、美味しいなら飲んだらいいです。熱中症予防で言われている多くのことは正しいですが、中には間違っていることもあります。特に、熱中症になった後の対処法と熱中症になる前の予防法の話を、ゴッチャにして喧伝している場合があります。対処と予防を、きちんと分けて説明することができていません。そしてその内容のなかには、予防法としては間違っているものがあるので気をつけなければないけません。そしてもしかしたら、その間違ったものを何かやっている可能性がね、あるかもしれないんですよ。何か不自然なことをね、あえてやるような…。」
「さあ、特に何もしていませんが…。」
寒府 (沢田流膝陽関) に反応が出ていることに気付いた。おそらくこれが原因だ。
じゃあ、なぜ寒府に反応が出たのか。
「なんか、 “さむっ” て思ったことありませんか?」
「さあ? 寒いと思ったことは…ああ、あります、娘のところで孫の面倒を見ていて、その時クーラーが少し寒いと思いました。」
「いつです? 」
「熱中症になる一週間前のことです。」
「うーん、それは違うなあ。パジャマは? どんなの着てる?」
「長袖と長ズボンです。薄い生地ですけど。」
「うん、それでいいです。そういう着方をしていれば、明け方に冷えるということはないんでね。…ちょっと分からないなあ。でもなんかで冷えてるのは確かなんです。基本的に熱中症は、普段から温かいものを飲食していれば、まずなることはないんですが…。当院の患者さんで、熱中症になったという話はまず聞かないんですよ。」
「その辺は、先生のご指導を守って気をつけています。」
「何かないですかね。何か不自然なことです。不自然な冷えることをすると、寒いと感じるセンサーが働かなくなる可能性があります。保冷剤で冷やしながら草引きをしたとか。」
「いえいえ、そんな事してないです。」
「そうですか。例えばね、暑い夏の日中に、川底のジャリをコンクリートの材料にと、運ぶ作業をしていた。すごい労働量です。普通なら夏の炎天下にこんな労働量はこなせないんですが、こなせる理由がある。川に足をつけているので、暑くないんです。で、こういうのが不自然だと言うんです。これは、本来の “動ける量” を遥かに超えているのに、ブレーキがかからない状態です。どこかを冷やしながら労働すると、体温が上がらないのでいくらでも動けるんですが、その分、労働量の制御ができなくなる。結果として無理のし過ぎで体調を崩してしまうことがあります。この高温下で生きている限り、高温を前提にするべきなんですね。」
「ああ、そしたらアレが原因でしょうか。そう言えば息子に勧められて、その前の夜、氷枕をして寝たんです。熱中症予防になると言われて…。そんなこと今までやったことなかったんですけど…。」
「ああ、やっと出たな。それです。深部体温を感知するのは、脳の奥にある視床下部です。深部の血液の温度を素早く察知するセンサーの役割をしていて、温度が低ければ “さむい” という感覚を自覚させて服を着させるなどし、温度が高ければ “あつい” という感覚を自覚させて服を脱がせるなどします。そうやって、低体温や高体温にならないようにする。その元締である視床下部の近く、つまり後頭部を氷で冷やすと言うことは、そこを0℃近くにしようとするということですね。そんなことをしたら、視床下部は “ああ、これは冬が来たのだな” と勘違いするでしょ? すると低体温にしない冬の体制が整い、高体温は前提にしません。ほんで、翌日は夏の猛暑です。自然というのは、冬の次は春、春を経て初めて夏が来るということになっている。冬からいきなり夏というのは、いくら賢い視床下部でも対応できないんです。冬だと思って油断していたら、知らん間に体温が上っちゃってた。だから熱中症になったんです。センサーが鈍くなっていたから、暑いと感じられなかったんですね。」
「ああ、そうなんですか…。あれが悪かったんですね…。私、人に勧められたらついやってしまうんです…。」
「みんなが言っているから正しいことだとは言えないですね。特に理系のえらい先生方は、勉強はよくお出来になるけれど、炎天下で労働したことがないでしょ? 実体験に乏しいんです。経験が伴わない。想像の域を脱していない。だから一見理論的に見えるかもしれないが、それはリアリティー (臨床) では使えません。薬でも認可を得ようと思ったら治験や動物実験が必要でしょ? なのにそういう実験をやっていない。現実に、先生方ご自身で炎天下労働をやってみたら分かると思います。ご自分が指導しておられる通りやっても、数時間で熱中症になります。そもそも皮膚温のことを言ってる先生って、見たことないですね。どうしたら熱中症にならないか、自分で実験していれば皮膚温に着目せざるを得なくなると思います。…もちろん、熱中症になってしまった後の対処法は、えらい先生方のおっしゃることで間違いないです。」
「クーラーはいいんでしょうか。」
「クーラーは全体を冷やすので危険が少ないです。危険が少ないということは、 “寒い” と感じることができるということです。寒ければクーラーを切ればいいんですからね。しかし、氷枕は局所的で、いくら局所が0℃近くになっていても “寒い” と感じられないんです。冷たいと寒いとは違うんです。猛暑の中では “冷たい” は却って心地よく感じます。しかし全身を0℃の水風呂に浸けたらすぐに寒くなりますね。だからずっとは入れないでしょ? だからこそ安全だということです。自然なことには体は防御反応を素早く出しますが、不自然なことには体は反応できないんですね。自覚できなければ不意打ちをくらうということです。」
「そうなんですね。」
「もちろんクーラーも効かせすぎて寒いのを辛抱する形になると危険ですので、一概に安全とは言えません。便利なものは上手に使う必要があり、下手に使うと危険になります。」
「そうですかー。わかりました。私の悪い癖なんですが、これこれが良いよって人に言われると、つい…。」
「とにかく、僕は体にいいことは全て言い尽くしています。だから初診に3時間も4時間もかけるんです。氷枕が体に良いのなら、こんな僕ですよ? 患者さん全員に勧めまくると思うんですね。でも、そんなこと僕が言いそうにないでしょ? 〇〇さんはもう3年もここに通っておられるんだから、何となく分かると思います。誰かに良いよって勧められて迷った時は、僕がどう言いそうか考えてみてください。そして慌てずに、僕に聞いてから、やるかやらないかを決めたらいいと思います。」
「なるほど、そうですね。わかりました。」
改めて、臨床とは難しい。
今回は、なんとか炙り出した。氷嚢だった。
だが、多くはここまでたどり着けない。たまたま氷枕をしたなどと、どうやって見抜くことができるだろうか。僕が見抜いたのは寒府の反応 (冷えの反応) だけである。その反応を見つけるだけでも難しいのに、その上その反応がなぜ出ているのか、問診によって具体的に炙り出さなければならないのである。十人十色の生活の足取りを、反応を元に「聞き出す」のである。この作業にどれだけの時間と労力がかかることか。だが、その労を惜しんでいては人助けなど思いもよらないことである。こういう労力を、いったいこの世の何人の治療家が注ぎ込んでいるだろうか。偉い先生方には、失礼を顧みず諫言申し上げたい。たとえお金にならなくても、この労を惜しまぬ姿こそが、医療に携わるものの基本だと思うからである。その基本なくして、どうやって熱中症すら未然に防ぐことができるだろうか。
夏の炎天下で労働することができる人は生命力の旺盛な人である。その生命力とは、その気温その労働に見合った汗をかく能力、そしてその汗に見合った水分を摂る能力、そしてその環境下で生命維持に必要な塩 (ミネラル) を保持する能力、そして筋肉から発した熱をその気温下で冷ますことができる能力である。汗の代わりにミストを浴びたり、水が飲めないから口当たりの良い甘味料入りのジュースを飲んだり、塩 (ミネラル) を途中で補充したりするのは、当座の付け焼き刃である。まして体温を下げるために氷を使うなどは、生命力がないくせにカラ元気をつけるようなものである。そもそも生命力がないのに、無理をしようとする時点でアウト、その労働を取りやめ、空調の整った部屋で大人しくしているべきである。
割り箸のような骨なのに筋肉ムキムキだとすぐに折れてしまうだろう。骨が割り箸ならば、それに見合った筋肉であるべきで、その筋力なら骨は折れない。骨 (土台) に見合わない力を出すと壊れてしまうのである。
その無理は、熱中症という形で出るとは限らない。持病の悪化で出ることもあるだろうし、感染症として出ることもある。
以上は、脈診で体に聞いて得た正否を元に、僕の実体験を加えた仮説である。僕は、休日ごとに真昼の炎天下で農作業を続けてきたこの10年で熱中症になったことが一度もないが、これも仮説を打ち立てる根拠の一つとしたい。さらに僕は、5分ウォーキングをしただけで冷や汗をかいて寝込んだ虚弱期から、夏の炎天下で昼食抜きで10時間ぶっ通しの農作業をやって却って体調が良いという壮健さまで、自分の生命力を上げた。こういう奇跡とも言える実体験を持つ僕が、そういう印象を持つということである。地獄から見聞し天国も知っている幅広さが大切である。同じ実体験を持つ人がもしいたら、その人からのご批判ならばお受けしてもいい。底辺から体をきたえ上げた人ならば、自ずと得るものがあるからである。

当該患者は3年来の患者さんであり、しかも本ブログの愛読者でもある。熱中症が落ち着いてすぐ、本ブログの「熱中症予防に関する考察」を読んだというくらい、勉強熱心な方である。そんな方をもってしても、この熱中症は防げなかった。
いかに世間からの雑音が大きいかだろう。
流されてはいけない。単純思考もいけない。
理論的に、なぜ体温が冷めなくなるのかを理解する。
その一助ともなればと、ご批判をも顧みず本ページを公開することとした。

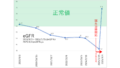

寒府の反応は、多くは皮膚の感覚神経で感じ取れる寒冷の刺激による悪影響を示す。マスコミではまだ聞いたことがないが、冷えが熱中症の原因になる…とは本ブログで強調するところである。まず、正常な体温の有り様は、深部体温と皮膚温の2つを考え合わせて評価する必要がある。結論から言うと、皮膚温が下がることが熱中症になりやすい条件となる。皮膚温が下がると言うことは、皮膚毛細血管が収縮しているということである。皮膚毛細血管が収縮すると、深部の太い血管を流れる熱い血液が、皮膚に到達できない。すると深部体温が上がってしまう結果となる。詳しく説明する。外気が30℃であるとしても、それは深部体温37℃よりも低い。よって熱い血液は皮膚毛細血管を経由することで冷まされ、冷まされた血液は深部に戻って深部体温をさますのである。もし皮膚毛細血管が機能していないと、熱い血液は冷まされることなく、深部のみをぐるぐる回ることになる。これは本ブログでは “魔法瓶状態” と呼んでいる。よって、皮膚温を温かく保つようにするのが熱中症にならないコツである (電気などで温めるのは不可、保温は可) 。そのために当院では冷たい飲食を控えること、寒ければクーラーを緩めるなり一枚多めに重ね着するなり対処することを推奨している。こういった原理をよく知らなければ対処法を知ったところで “一つ覚え” になってしまい、盲点が生じる危険がある。「熱中症予防に関する考察」では、原理を詳しく説明したつもりである。ぜひ熟読してもらいたい。批判があってもお慌てにならず、まずはご熟読いただいてから後にお伺いしよう。
皮膚温 (四肢末端を含めた表面温度) を温かい状態に改善することは、ガンにもアレルギー疾患にも感染症にも、ありとあらゆる病気を治すうえでもっとも注目すべきことである。まじめに医療を行い実を上げておられる先生ならば、よくご存知のことだろう。